画像引用元:アイボット公式サイト
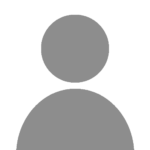 30代・男性
30代・男性近くの家電量販店ではルンバ j7+がもう置いてなくて…。やっぱり販売終了なんですか?



そう思う方、実は多いんです。でもご安心ください!ネットではまだ購入できるお店もありますし、用途によっては別モデルの方が合うこともあるんですよ!
最近、店頭でルンバ j7+を見かけなくなり、「もしかしてもう販売終了?」と不安に感じた方も多いのではないでしょうか。実際、家電量販店の棚からは消えつつありますが、ネット通販ではまだ在庫がある店舗も存在します。
とはいえ、購入前に知っておきたいのが、「販売終了の背景」や「水拭き機能の有無による影響」、そして「他のモデルとの違い」です。
この記事では、今だからこそ知っておきたいj7+の全体像を、初めての方にもわかりやすく解説していきます!
- ルンバ j7+が販売終了といわれる理由とネットで買える現状
- 水拭き機能の有無で何が変わる?必要かどうかの判断ポイント
- 類似モデルとの違いと、今選ぶべきおすすめモデル
ルンバ j7+販売終了はなぜ?


画像引用元:アイボット公式サイト
急に見かけなくなった理由とは?
「最近ルンバ j7+を全然見かけないんだけど、まさか販売終了…?」家電量販店やECサイトでそんな声が広がっています。
実際に「在庫限り」「終売予定」などの記載が増えており、事実上の販売終了に近い状況といえます。では、なぜルンバ j7+が販売終了となるのでしょうか?
公式情報や市場動向をもとに、分かりやすく解説します!
後継モデル「Combo j7+」「j9+」への切り替えが進行中
ルンバ j7+の販売終了が囁かれる最も大きな理由は、後継モデルの登場です。
iRobotの販売戦略と新製品の展開
iRobotは2024年以降、吸引+水拭き機能を両立した「Roomba Combo」シリーズを主軸とした展開に移行しています。特に注目されているのが以下の2モデルです。
| モデル名 | 発売年 | 特徴 | 水拭き | 自動ゴミ収集 |
|---|---|---|---|---|
| Combo j7+ | 2024 | j7+の進化版 | ◎ | ◎ |
| Combo j9+ | 2025 | 最上位モデル | ◎自動モップ展開 | ◎ |
📌【出典】iRobot公式製品
これらのモデルが登場したことで、j7+は旧型機種として流通在庫限りの扱いになっている可能性が高いと考えられます。



シリーズの進化スピードが速いiRobotでは、販売終了=サポート打ち切りではないのでご安心を!
j7+は本当に終売?公式情報は?


画像引用元:アイボット公式サイト
2025年4月現在、iRobot公式サイトでは**「j7+の生産終了」などの明記はなし**。ただし、製品ページが縮小されており、新製品がメインに表示されている状態です。
店頭や通販サイトの動きから見えてくること
- Amazon、楽天、ヨドバシカメラなどでは「在庫限り」の表記が目立つ
- 一部店舗では価格が下がり「処分価格」に近い扱い
- iRobot公式ストアでの表示順位も下位に移動
この動向から見ても、新製品への在庫切替を進めていることは間違いないといえます。



在庫切り替えの今がチャンス!
買うなら今?j7+の強みと今後の価値
販売終了が近いとなると「じゃあ今さら買う意味はないの?」と思われるかもしれませんが、実は“今だからこそお得”な理由もあります。
j7+の主な魅力ポイント
- 自動ゴミ収集ベース付きで手間なし
- AIカメラで障害物を見分けて避けてくれる
- ペットの排泄物などを認識する「Poop Detection」搭載
今後の選び方と戦略的な買い替え判断
ルンバ j7+が向いているユーザー
- 水拭きは必要ない(フローリング中心)
- コスパ重視で自動収集機能を取り入れたい
- 在庫処分価格で良品を手に入れたい
最新モデルが向いているユーザー
- 水拭きまで1台で済ませたい
- モップ自動展開・洗浄など全自動にこだわりたい
- 価格よりも利便性を最優先したい



「最新モデルも気になる方へ」
吸引+水拭き両方に対応したハイブリッドモデルも人気急上昇中です!
ルンバ j7+は“過渡期の優秀機種”
現在のルンバ j7+は、「吸引特化モデルの完成形」ともいえる完成度を誇ります。
ただし、これからの主流は吸引+水拭きのハイブリッド化。
- 水拭きはいらないから価格を抑えたい人にはj7+がベスト
- 1台で完結させたい人はCombo j7+やj9+が👌
このように、「販売終了」=「選んではいけない」ではありません!むしろ、“過渡期だからこそお得”なモデル、それがルンバ j7+です。
ルンバ j7+は水拭きしないとダメ?
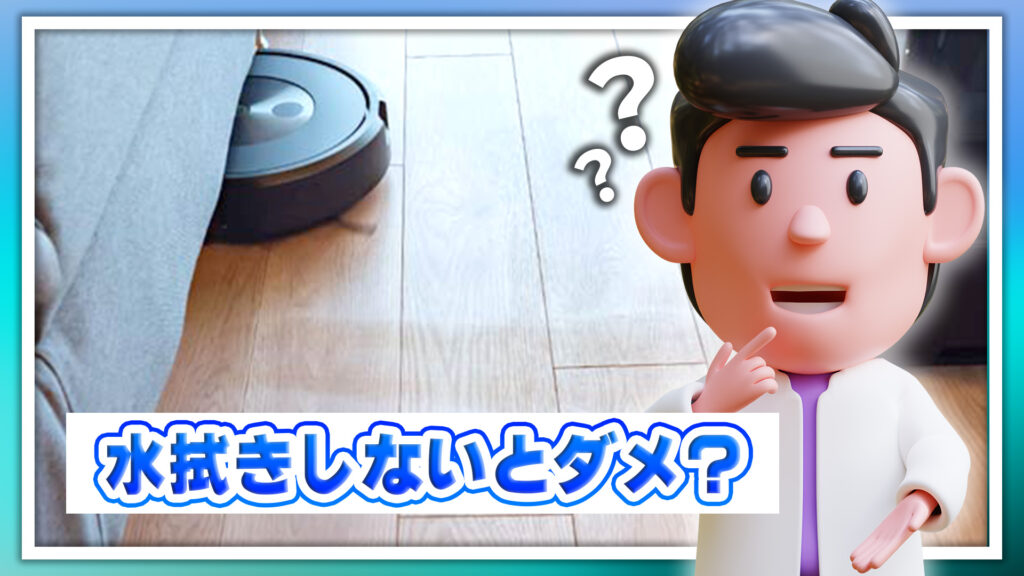
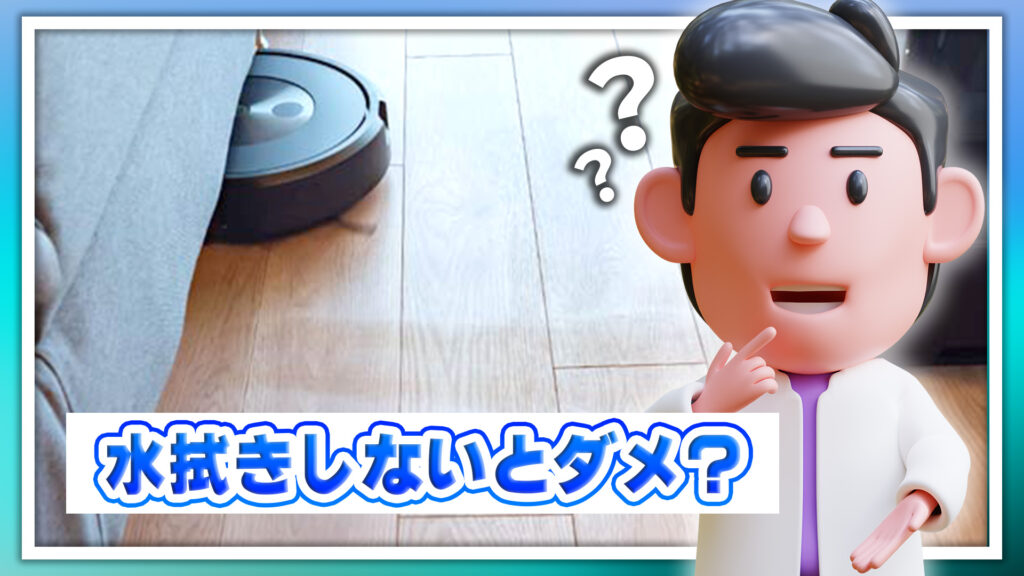
画像引用元:Joshin公式サイト/試用レポートページ
吸引掃除だけでは不十分なのか?
ルンバ j7+は吸引力に優れたロボット掃除機ですが、「水拭き機能がない」点が一部のユーザーにとって懸念点になっています。
特に以下のような疑問を持つ方が増えています。
- 「吸引だけで床の衛生は保てるの?」
- 「見えない汚れはどうなる?」
- 「小さな子どもがいる家庭では水拭きが必要?」
そこでこの章では、ルンバ j7+に水拭きが不要なのかどうか、あらゆる角度から検証していきます。
水拭きが必要とされる背景とは?
生活環境で蓄積する“見えない汚れ”
掃除機で吸い取れるのは、ホコリ・髪の毛・細かいゴミなど「乾いた粒子状の汚れ」が中心です。しかし、実際の生活空間では以下のような油分・湿気を含む汚れが床に付着します。
| 汚れの種類 | 原因 | 掃除機で除去可能か |
|---|---|---|
| 足裏の皮脂 | 素足での歩行 | ✕(水拭きが有効) |
| 食べ物の飛び散り | 子ども・ペット | △(拭き残りが多い) |
| 調味料や飲み物 | キッチン・リビング | ✕ |
これらは吸引だけでは完全には除去できず、床のザラつきやベタつきの原因になります。



見た目がきれいでも、足裏で“あれ?ザラザラしてる?”と感じたら水拭きが必要なサインです!
床材によって必要性は異なる
実は、水拭きの必要性は床材の種類によっても変わります。
素材別・水拭き掃除の相性一覧
| 床材 | 水拭きの有効性 | 備考 |
|---|---|---|
| フローリング(木) | △ | 乾拭き推奨、水拭きは月数回 |
| クッションフロア | ◎ | 水拭きに強く、油汚れにも効果的 |
| 畳 | ✕ | 水拭き不可、乾拭きまたは掃除機 |
| タイル・石材 | ◎ | 雑菌除去に水拭きが有効 |
特にマンションや新築住宅に多いクッションフロアやタイル床では、水拭きの効果が極めて高いといえます。



「クッションフロアなら、吸引だけじゃもったいないかも!」
👉 水拭き対応モデルはこちら!
衛生面での水拭きの意義とは?
細菌・ウイルス対策としての水拭き
床は、ウイルスや菌が付着しやすい場所の一つであり、特に小児科や保育施設では、拭き掃除による清掃が一般的に行われています。感染症対策として、手洗いや消毒の徹底とともに、床や手が触れる場所の清掃が重要とされています。
家庭ではそこまで厳密な対応は不要ですが、水拭きにより雑菌の除去やアレルゲンの軽減効果が期待できることは明らかです。



赤ちゃんやペットがいる家庭では、水拭き掃除を定期的に入れるだけで衛生レベルがぐっと上がりますよ!
吸引掃除で充分なケースもある
水拭き不要でも問題ない生活スタイル
- 土足禁止で床が清潔に保たれている
- 飲食がダイニングのみで汚れが限定されている
- 毎日ルンバで吸引掃除を実施している
- ペット・子どもがいない
このような環境では、ルンバ j7+の吸引力だけでも十分に対応可能です。
また、日常的にウェットシートなどで部分的な拭き掃除を併用すれば、わざわざ水拭き機能付きモデルに切り替えなくてもOKという選択肢もあります。



最低限の手間で清潔を保ちたい方は、j7+と部分拭きの組み合わせがおすすめです!
ルンバ j7+は水拭きしないとダメなのか?
結論としては、「生活スタイル次第」です。
- 拭き掃除の重要性が高い家庭(子育て・ペット・油汚れ)では、水拭き対応モデルの方が理想的
- 吸引だけで十分な家庭(汚れが少ない・部分拭き併用)では、ルンバ j7+の機能で必要十分



水拭きが“ダメ”というより、“必要かどうか”を見極めることが大切です。あなたの家の床、実はもっと汚れてるかも…? 👉 今の生活に合ったルンバを選ぶならこちら!
ルンバ j7+のデメリットや類似品は?
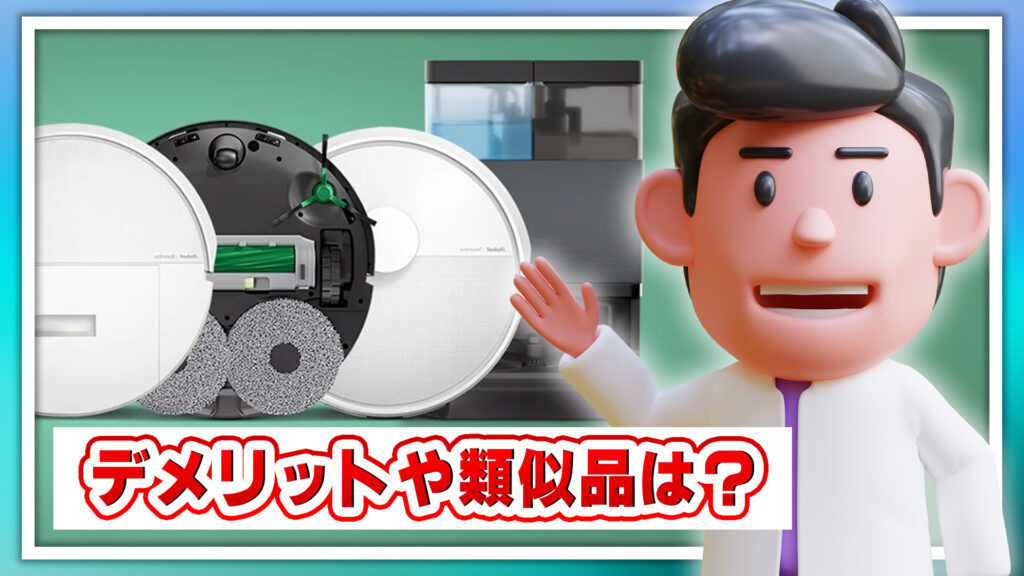
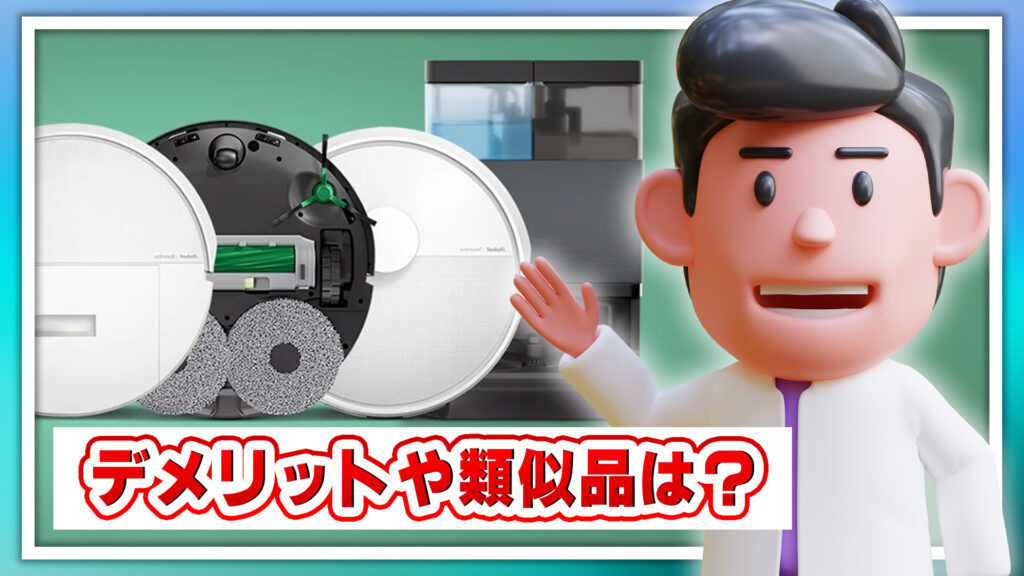
画像引用元:アイボット公式サイト
購入前に知っておきたい注意点と選び方のコツ
ルンバ j7+は高性能なロボット掃除機として人気ですが、「完璧なモデル」ではありません。実際に使用した方のレビューや、専門家の分析からも、機能・価格・運用性に関する課題が見えてきます。
ここでは、ルンバ j7+のデメリットを客観的に整理しつつ、他社製品との違いや選び方のポイントを詳しく解説します。
デメリット1:水拭き非対応
最大の弱点は「水拭きができない」こと。
吸引性能はトップクラスですが、皮脂や油分、ベタつき汚れは吸引だけでは取り切れません(詳細はBで解説)。そのため、水拭き機能が欲しい場合は別機種との併用や買い替えが必要になります。



掃除は“見えない汚れ”との戦い。吸引だけでOKな家もあれば、水拭きが必須な環境もありますよ!
デメリット2:初期設定・操作が複雑に感じる人も
ルンバ j7+はスマホアプリで詳細な部屋マッピングや清掃設定が可能ですが、アプリ操作に不慣れな方や高齢のご家族にはやや扱いにくいという意見も見られます。
- アプリ連携に時間がかかる
- Wi-Fi設定がうまくいかない
- 掃除エリア指定が面倒に感じる
操作を簡単に済ませたい方は、物理ボタン操作もできる機種や、設定が最小限で済むモデルを検討するのも手です。
類似品のスペック・機能を徹底比較!
吸引力+利便性+水拭き対応の点から、ルンバ j7+とよく比較される製品を一覧にまとめました。
代表的なロボット掃除機比較表
| 製品名 | 水拭き | ゴミ自動収集 | マッピング | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ルンバ j7+ | ✕ | ◎ | AIカメラ搭載 | 吸引特化・障害物認識が強み |
| Combo j7+ | ◎ | ◎ | カメラ | 1台完結型 |
| ルンバ i3+ | ✕ | ◎ | ジャイロ式 | コスパ重視 |
| DEEBOT T10 OMNI | ◎ | ◎ | レーザー | モップ自動洗浄あり |
| Eufy Clean X9 Pro | ◎ | ✕ | カメラ+AI | 床材に応じてモップ圧自動調整 |



「各社進化がすごい!」最新機種の中には、水拭きモップの“自動洗浄・乾燥機能”付きも登場しています。
あなたに合った選び方のポイント
「どれがいいのか迷う…」という方は、以下のライフスタイル別チェックポイントを参考にしてみてください。
タイプ別おすすめモデル
| タイプ | おすすめモデル | 理由 |
|---|---|---|
| 初心者・簡単操作希望 | ルンバ i3+ | シンプル設定・安定動作 |
| 吸引メイン+価格重視 | ルンバ j7+ | 高性能吸引+ゴミ収集 |
| 吸引も水拭きも1台で | Combo j7+ / T10 OMNI | オールインワン構成 |
| コスパ重視+水拭き対応 | Eufy Clean X9 Pro | 機能充実・価格控えめ |



「どれを買えばいいか分からない…」自分の“掃除スタイル”や“床材”を整理すると、必要な機能が自然と見えてきますよ!
まとめ|ルンバ j7+は今こそ見極めどき!
ルンバ j7+は、吸引力・自動ゴミ収集・障害物回避に優れた高性能モデルとして多くのユーザーに愛用されています。しかし現在は、後継機種の登場により販売終了が進行中であり、店舗によっては「在庫限り」となっているケースも。
また、水拭き機能が搭載されていないことから、家庭環境によっては別機種や併用が必要になる点にも注意が必要です。
とはいえ、吸引機能だけで十分な家庭や、部分的な拭き掃除で対応できる方にとっては、今がもっともお得に手に入れられるチャンスとも言えます。



「買うなら今がチャンス!」
在庫限りの価格で手に入るルンバ j7+、あなたの暮らしに合うかどうか、もう一度チェックしてみてくださいね!
880 – 2 390 - 0 210 – 2








コメント